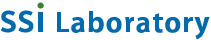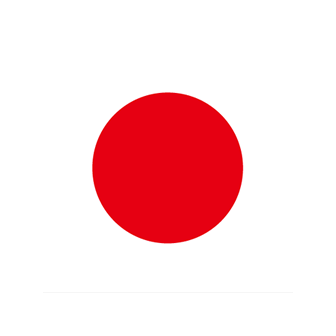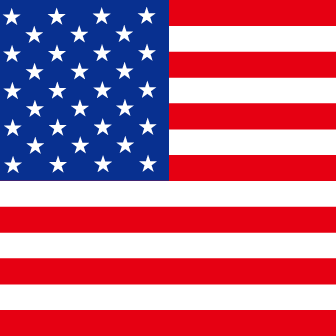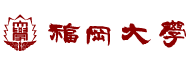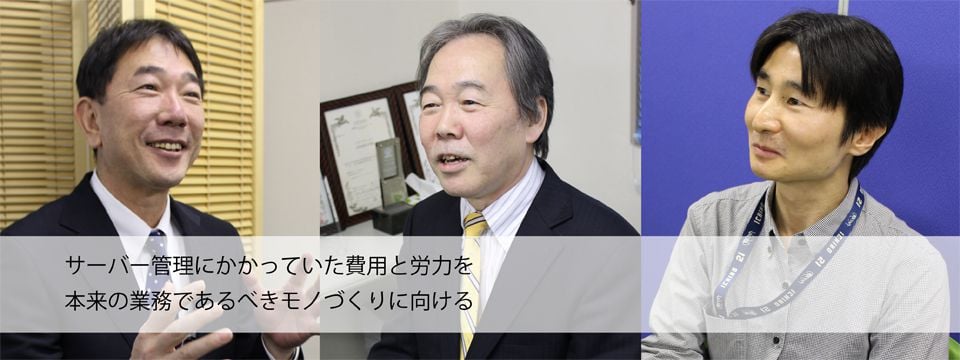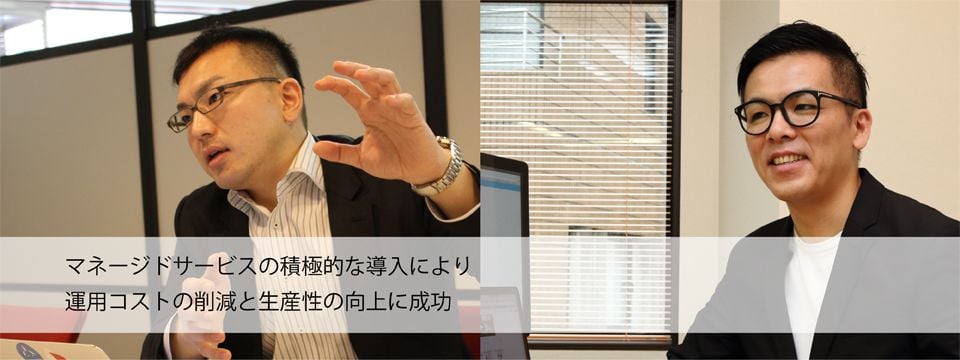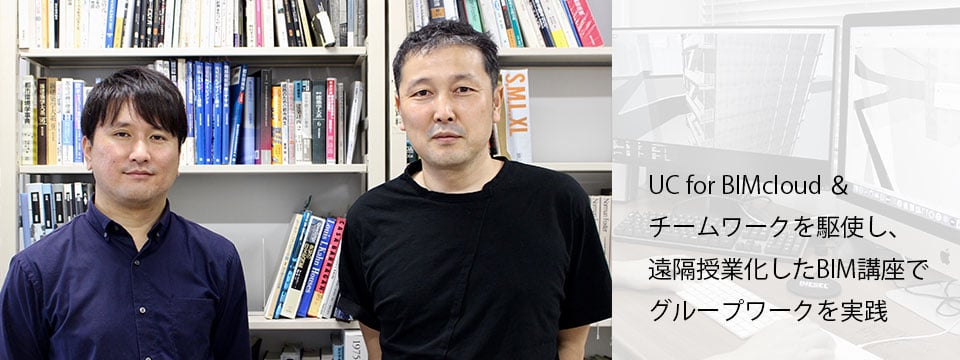
学校法人 福岡大学 様
福岡県福岡市に本部を置く福岡大学は、約2万人の学生を擁する西日本最大級の私立総合大学です。9学部31学科に及ぶ学部の中でも、工学部建築学科は建築に関わる広汎なフィールドを幅広く学べるコースとして人気を集めています。同学科では、最新のBIM教育についてもいち早く2019年からARCHICADを導入し、独自の講座を開設しています。
2020年4月、新型コロナ対策の緊急事態宣言を受け、福岡大学は全授業の遠隔化を決定。このBIM講座も遠隔手法となりました。SSIラボでは、その運用を円滑化するためクラウド基盤として「UC for BIMcloud(R)」を提供しています。導入経緯と運用について、准教授の宮崎慎也博士と講師の吉田浩司氏(株式会社ixrea 代表取締役)、また、建築学科2年のカン テウさん、恒冨春香さん、飯田愛華さんにお話を聞きました。
UC for BIMcloudの導入背景
学生たちが自ら使い始めた ARCHICAD を導入し、いち早くBIM講座を開始。ところがコロナ禍で全授業リモート化の非常事態に。
 |
|
福岡大学 工学部 建築学科 准教授 博士 |
|---|
|
宮崎 慎也 博士 |
 |
|
講師/株式会社ixirea 代表取締役 |
|---|
|
吉田 浩司 氏 |
 |
|
建築学科2年 |
|---|
|
恒冨 春香 さん |
 |
|
建築学科2年 |
|---|
|
カン テウ さん |
 |
|
建築学科2年 |
|---|
|
飯田 愛華 さん |

リモート講義の模様
――授業にBIMを取り入れたのはかなり早い方ですね
宮崎慎也氏(以下 宮崎氏) 私たちがBIMを意識したのは3年ほど前からですが、そのきっかけは実は学生たちで……いつの間にか彼らが勝手にARCHICADを使い始めていたんですよ。それまでCAD製図の授業ではフリーウェアのJw_cadを使っていたのに、学生はARCHICADばかり使うようになって。一方ではBIMについて、構造の先生方からも「建築業界で広まっている」「施工現場でも使われている」という声が上がるなど社会的ニーズを感じたため、これを機にARCHICADでしっかりBIM教育を行っていこう、ということになりました。
――学生がARCHICADを使い始めた理由は?
宮崎氏 当時、Jw_cadと合わせてSketchUpも使い「3Dでパースを描きなさい」といった課題を出していましたが、このやり方だと学生はJw_cadで図面を描き、さらにSketchUpで3Dモデルを立上げる2度手間を避けられません。そのため彼らの間で「ARCHICADで描けば1度で済むから楽だ」という話が広がったようです。ちょうどARCHICADが学校関係へ無償提供されていたこともあり、一気に普及しました。つまり、意識の高い学生が頑張って使い始めたのではなく、近道したい学生が広めたのです(笑)。
――初のBIM講座、先生方も大変だったでしょうね
宮崎氏 実は当初、私たちも「2次元CADで断面図等をきちんと描く方が大事」みたいに思っていましたが、こうなるとこちらも変わらざるを得ません。学生もBIMイコール単純な3Dモデラーみたいな把握の仕方で総合的な部分を分かってないし、授業でBIMの概念から使い方まできちんと系統立てて教えるべきだと考えました。で、当時はARCHICADを使える教員がいなかったので吉田先生をお招きしました。

リモート講義の模様
――お二人で作ったBIMの授業はどのような内容でしょうか
宮崎氏 2年生前期の選択科目で「建築情報」という講座です。1回90分の授業を週2回で計15回行います。最初の5回は基礎としてBIMの概念の話をし、6回目からは教科書に沿ってツールの使い方を一つ一つ固めていきます。まず「自分が作った住宅作品をモデリングしてみよう」ということでARCHICADを使って入力してもらう。そして、最後の5回で学生2〜3人のチームで、天神に超高層ホテルを建てるという設計課題をやってもらいます。
吉田浩司氏(以下 吉田氏) まあ、半期の授業だし教えられるのはBIMの「さわり」の部分程度です。ちょっとした操作でモデリングでき、図面をアウトプットできる所まで……ただ、それを3Dモデラーの延長と捉えてほしくないわけで。あくまでBIMとして、モデルに「情報」が足されていくこと、そして、その情報がアウトプットされることまで意識してもらいたいのです。そのため、たとえば成果品もPDFだけでなくBIMxでも提出させています。BIMxのインターフェースは情報をリアルに引き出せるので、BIMでは2次元図面から最終的にこれに変わっていく、ということを意識してほしいのです。
――UC for BIMcloud導入のきっかけはやはり新型コロナですか?
宮崎氏 そうですね。緊急事態宣言が出されるとすぐ全授業のリモート化が決まって……。ただ、この講座は当初それほど影響ないと思っていました。通常はPC教室で前方に先生のパソコン画面を映し、学生はそれを見ながら各自パソコン画面に向かうので、リモートになってもさほど変わりません。心配だったのは各学生の自宅PCのスペックと通信環境くらいです。ただ、後半の、グループで取り組む応用課題でいろいろ問題が出てきました。
UC for BIMcloud+チームワークの活用
UC for BIMcloudを採用しARCHICADのチームワーク機能をフル活用! 新たなBIM時代のチーム設計スタイルを学生たちが実践しました。

リモート講義の模様
――どのような問題が発生したのですか?
吉田氏 この応用課題は何人かでチームを組み、協力しながら一つの課題を作っていきます。去年までは教室内で各自が基準階など作り、それをホットリンクで結んで、その場でコミュニケーションをとってやりとりしていました。ところが現在は学生たちが同じ空間に居ないため、「チーム内のデータ共有をどう実現するか?」が問題になったわけです。大学のストレージでデータ共有することもできますが、それでは同時並行で作業できませんし……。
そこで着目したのがARCHICADの「チームワーク」機能です。ARCHICADの機能の一つで、これを使えば1個のモデルデータを複数のユーザーが同時に確認、編集できます。ただし、学校のサーバーでチームワークを組むのはセキュリティの問題等があってハードルが高く、難しそうでした。そこでいろいろ検討して辿り着いたのが、エスエスアイ・ラボの「UC for BIMcloud」でした。
――UC for BIMcloudはARCHICADプロジェクトをクラウドで共有するグラフィソフト認定のサービスです。作業場所やプロジェクト規模に関わらず、リアルタイムでチームワークによる共同作業が可能になります
吉田氏 実は私の会社では、UC for BIMcloudを導入して、設計者の誰もが日常的にこのチームワーク機能を活用しており、使いやすさは体験済みでした。現在では、当社のチーム設計において欠かせない機能となっています。今回あらためて教員としての視点で見ても、教わる側だけでなく教える側も同時に進行中のモデルデータへ入れるなど、非常に大きなメリットがありました。たとえば学生から「これができない」「このやり方が分らない」「ちょっとここがエラーに」と言われたら、すぐに私たち自身が彼らのデータにアクセスして確認できるわけで、オンライン指導しやすいのです。で、たまたま3カ月無料のキャンペーン期間中だったので「3カ月だけやってみませんか」と宮崎先生に相談を持ちかけました。それが5月末で、6月後半からは応用課題が始まるタイミングでした。なので承認後はエスエスアイ・ラボにもスピード感を持って対応いただき、6月頭には環境が完成しました。
――新システムの導入だけに心配だったのでは?
宮崎氏 そのあたりは吉田先生にお任せしていたので(笑)。懸念といったら、学生が付いて来られるか?ってことくらいでしたね。
吉田氏 確かに当初はチームワークやUC forBIMcloudを使う予定はなかったので、学生には説明しませんでした。ところが急遽使うことになって、応用課題初日に「こういう機能を使います」と、1時間ほどログインの仕方から使い方を説明しただけです。それでも操作に関して質問等はなく、学生たちは最初からすんなり使えていた印象です。実際、その後もチームワーク機能に関してつまずく学生はいませんでした。
――対面型の授業と比べていかがでしたか?
宮崎氏 PC教室で隣どうし座っていても作業するにはホットリンクが必要だし、時間内に終わるとは限らず、学生たちは結局、家に持ち帰って作業するケースも多かったんです。すると3人のチームで、ある人が作った1階と別の人が作った2階がズレてしまうなんてことが少なくありません。ネット経由でも同時並行で一つのモデルを作っていけばそれはないわけで。逆に学生にとってやりやすかったんじゃないかと思います。
吉田氏 対面授業なら学生のPC画面を見て「ここはこうだね」と指導できましたが、リモート授業ではそれもなかなかリアルにはできません。ところがチームワークを使えば、対面授業と同じようにやれるのです。これはとても良かったですね。
導入効果と今後の展望
ARCHICADによるBIM作業にチームワークとUC for BIMcloudは必須。皆さんは、なぜこんな便利な機能を使わないのですか?

UC for BIMcloudとARCHICADのチームワーク機能を使用して学生が制作
――では、実際に課題に取り組んだ学生さんに聞いてみましょう
恒冨春香さん(以下 恒冨さん) はい、私たちは3人のチームで高層ホテルの課題に取り組みました。テーマは「グラデーション」。個性の違う3人の意見がまとまってさまざまな色に移り変わっていく、という思いを込めており、ホテル内の廊下がカラーグラデーションになっているのが特徴の一つです。
――どのように作業分担して進めましたか?
恒冨さん 私が全体の役割分担を考え、それぞれに仕事を割り振って進めました。各階に客室と共用部分があるので、客室は部屋数を3等分し「それぞれ自由に作っていいよ」って感じで任せ、共用部分も作りたい所を作ってもらうなど、自由に取り組んでもらいました。
――3人の意見の調整や変更、修正など大変だったのでは?
カン テウさん(以下 カンさん) この講座の授業の中でチーム課題が一番楽しく役立ちました。テレワーク授業はいろいろ受けましたが、とにかくこのチームワークが便利で。細部の修正など、メールで指示してもなかなか正確に伝わりませんが、チームワークで同じモデルを見ていれば、すぐ対応して3人で確認し合えます。テレワークではこの機能が一番使われるのではないか、と思えるほど便利でした。
飯田愛華さん(以下 飯田さん) もちろん3人それぞれ考え方は違いますが、だからこそ、みんながデザインした客室の違いがすごく面白くて。チームワークで作業していればそれをすぐに3Dで見られるし、やり取りもオンラインでスムーズに進められる。楽しかったですね。
恒冨さん チームワークを使ったおかげで、一人一人の長所短所を上手く活かしたりカバーしたりできたかな、と思います。自分が苦手な所はメンバーに「お願いします」と任せられるのがすごく良いし、間違えた所を修正して貰うのもスムーズで。何というかすごく「チームで作っている」実感がありました。
――チームワークの操作は難しくありませんでしたか?
カンさん 基本操作を教えていただいて、すぐチーム課題に取り掛かりましたが、操作はそれほど難しい所もなく、3人とも十分できていたと思います。このチーム課題の開始時、吉田先生が「チームワークを知ったら、もう個人作業ができなくなるくらい便利だ」と仰有ったんですが、実際にみんなと課題を進めながら、先生の言葉通りの「便利さ」を実感しました。現役の設計者の方が使ったら、きっと他のやり方はできなくなるんじゃないかな、と思うほどです。
飯田さん 私もカン君と同じで、一回使ってみたらもう……。とにかく隣りに座って話し合いながら進めるよりずっとやりやすいし、作業そのものもより早く進む感じです。社会に出れば作業効率が大事になると思うので、これからもどんどん使っていくべきだなと感じました。
恒冨さん パーツを確保したり開放したりのやり取りは頻繁に行いましたが(笑)、それ以外は役割分担してやれば操作は難しくありません。「ここをよろしく!」みたいに分担していけば、本当に通常のARCHICAD操作と変わりません。後はそうやって頼んだことをちゃんとやってもらえれば、完成するので……全然難しくないですよ。

――学生さん達には好評のようですが、先生方いかがですか?
吉田氏 チームワーク導入を躊躇している設計者に、彼らの声を聞かせたいですね(笑)。とにかく今回のようなオンラインのグループワークで「ARCHICADで課題を」という授業では、UC for BIMcloud+チームワーク以上の方法はありません。よほどの資金を投入しサーバーを用意して、というなら別ですが、実際はそこまで設備投資できないでしょうし。その意味では、このやり方でなければできない授業でした。
宮崎氏 コロナ禍の影響を含め、来年どうなるかは未定ですが、いろいろ考えていることはあります。たとえば、この講座はPC教室のキャパシティで受講者数も40人程度に制限していましたが、リモートが可能なら大幅アップできます。100人規模だって考えられますね……むしろ、そうなった時に私たち教員が対応しきれるか? それがいま一番の課題かもしれません。